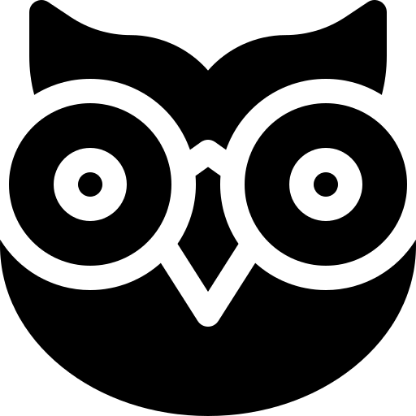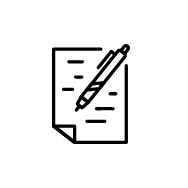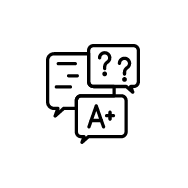【本の紹介】「パソコンとヒッピー」”コンピュータの民主化”に挑んだ異端者たちの物語
パソコン関連の書籍の中では、ちょっと変わった視点での本を読みました。
「パソコンとヒッピー」(原作:赤田祐一、初版発行:2025年4月25日)という本です。
表紙には「パソコンを抱えたサルが荒野を歩いている絵」が描かれています。
帯には『「デジタル技術は、人の意識を拡張する効力のあるLSDと似たツールである」―――ヒッピーたちのこの大胆な発想がアメリカ西海岸のハッカーに受け継がれ、コンピュータのパーソナル化が実現したというのは、よく知られた話だ。では、カウンターカルチャーとテックカルチャーという異なる二つの文化は、いつ、どこで、どのようにして交わったのだろうか。パソコンの誕生に情熱を注いだ人々のドラマに焦点を当てながら、その知られざる源流をたどる。』と書いてあります。
ヒッピーと言えば、1960年代のベトナム戦争に疑問と怒りを感じた若者がLove&Peaceや精神世界への回帰といったカウンターカルチャーを連想します。私が多感な時期に影響を受けたビートルズの『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』やジョン・レノンの「Power to the People」などに繋がるムーブメントとして関心を持っていました。
そして今はパソコン教室のインストラクターを職業としているため「パソコンとヒッピー」というタイトルと帯のメッセージを読んで迷わずに購入し一気に読みました。
本に書かれている内容から一つの逸話を紹介します。
1975年に販売された世界初の一般消費者向けマイクロコンピュータのキット「アルテア8800」でプログラムを実行するとそばにあるラジオが反応しノイズ音が鳴りました。プログラミングとノイズ音のパターンをハックした若者がビートルズの「The Fool On the Hill」をプログラミングで演奏させることに成功し「自分でつくることができて、数字の計算だけではない、実際に何かを実行できるコンピュータが出現」したことに拍手と歓声の嵐が起こったそうです。
――
50年が経ち、パソコンに関するテクノロジーは飛躍的に進化しました。インターネットで一瞬に世界中と繋がることができて、モバイルデバイスをどこにいても利用できます。さらに現在は生成AIの登場により、新たな活用シーンが増え続けています。
日々の利用シーンでは、パソコンのツールの操作方法のようにミクロの視点にとらわれがちですが、そもそも何のためにパソコンに関心を持ったのか、パソコンを使って実現したいことは何か、といったマクロな視点に目を向けるきっかけとなる本でした。
皆さんはこの夏、どんな本を読みますか? 猛暑の中、涼しい部屋の中での読書もおすすめです。
※参考URL:『パソコンとヒッピー』ができるまで
https://note.com/spectator_note/n/nbab088c69cb9