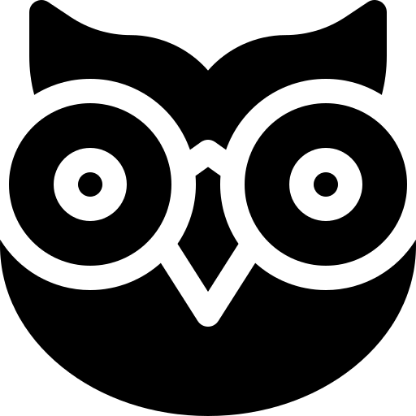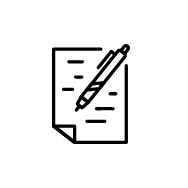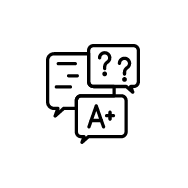【Excel】IF関数とIFS関数の違い
Excelで条件によって表示を切り替えたいとき、よく使われるのが「IF関数」。
最近では、Excel2019以降で使える「IFS関数」も登場し、「ネストが深くなって読みにくい…」という悩みを解消する選択肢として注目されています。
今回は、IF関数とIFS関数の違いを整理してみましょう。
●IF関数とは? IF関数は、「条件が真か偽か」で表示を切り替える基本の関数です。
例:点数によって合否を判定
=IF(A1>=60,"合格","不合格")
・シンプルな条件分岐にぴったり
=IF(A1>=80,"優",IF(A1>=60,"良",IF(A1>=40,"可","不可")))
・複数条件を扱うときは、IF関数を入れ子(ネスト)にして記述する必要がある
・ネストが深くなると、構造が複雑になり、修正や確認が大変になることも
●IFS関数とは? IFS関数は、「複数の条件」を順番にチェックして、最初に真になったものを表示する関数です。
Excel2019以降で利用可能です。
例:点数によって評価を判定
=IFS(A1>=80,"優",A1>=60,"良",A1>=40,"可",TRUE,"不可")
・条件と結果を並列に書けるので、ネスト不要で読みやすい
・どの条件にも一致しない場合は、最後に TRUE を使って簡潔に指定可能
・ネスト構造を避けたいときに便利
・読みやすさだけでなく、修正や確認のしやすさも向上する
★こんなときにおすすめ!
・IF関数:シンプルな条件分岐、古いExcel環境、他関数との組み合わせが多いとき
・IFS関数:複数条件をスマートに処理したいとき、ネスト構造を避けたいとき、読みやすさ重視の資料作成時
「IFが入り組んでしまって、どこが間違ってるのか分からない…」という声もよく聞きます。
IFS関数を知っておくと、そんな悩みもスッキリ解決できます!
ぜひ、実際のレッスンや業務でも試してみてくださいね!
最近では、Excel2019以降で使える「IFS関数」も登場し、「ネストが深くなって読みにくい…」という悩みを解消する選択肢として注目されています。
今回は、IF関数とIFS関数の違いを整理してみましょう。
●IF関数とは? IF関数は、「条件が真か偽か」で表示を切り替える基本の関数です。
例:点数によって合否を判定
=IF(A1>=60,"合格","不合格")
・シンプルな条件分岐にぴったり
=IF(A1>=80,"優",IF(A1>=60,"良",IF(A1>=40,"可","不可")))
・複数条件を扱うときは、IF関数を入れ子(ネスト)にして記述する必要がある
・ネストが深くなると、構造が複雑になり、修正や確認が大変になることも
●IFS関数とは? IFS関数は、「複数の条件」を順番にチェックして、最初に真になったものを表示する関数です。
Excel2019以降で利用可能です。
例:点数によって評価を判定
=IFS(A1>=80,"優",A1>=60,"良",A1>=40,"可",TRUE,"不可")
・条件と結果を並列に書けるので、ネスト不要で読みやすい
・どの条件にも一致しない場合は、最後に TRUE を使って簡潔に指定可能
・ネスト構造を避けたいときに便利
・読みやすさだけでなく、修正や確認のしやすさも向上する
★こんなときにおすすめ!
・IF関数:シンプルな条件分岐、古いExcel環境、他関数との組み合わせが多いとき
・IFS関数:複数条件をスマートに処理したいとき、ネスト構造を避けたいとき、読みやすさ重視の資料作成時
「IFが入り組んでしまって、どこが間違ってるのか分からない…」という声もよく聞きます。
IFS関数を知っておくと、そんな悩みもスッキリ解決できます!
ぜひ、実際のレッスンや業務でも試してみてくださいね!